- 営業時間
9:00~20:00
※土曜・日曜は12時まで営業 - 定休日
木曜・祝日
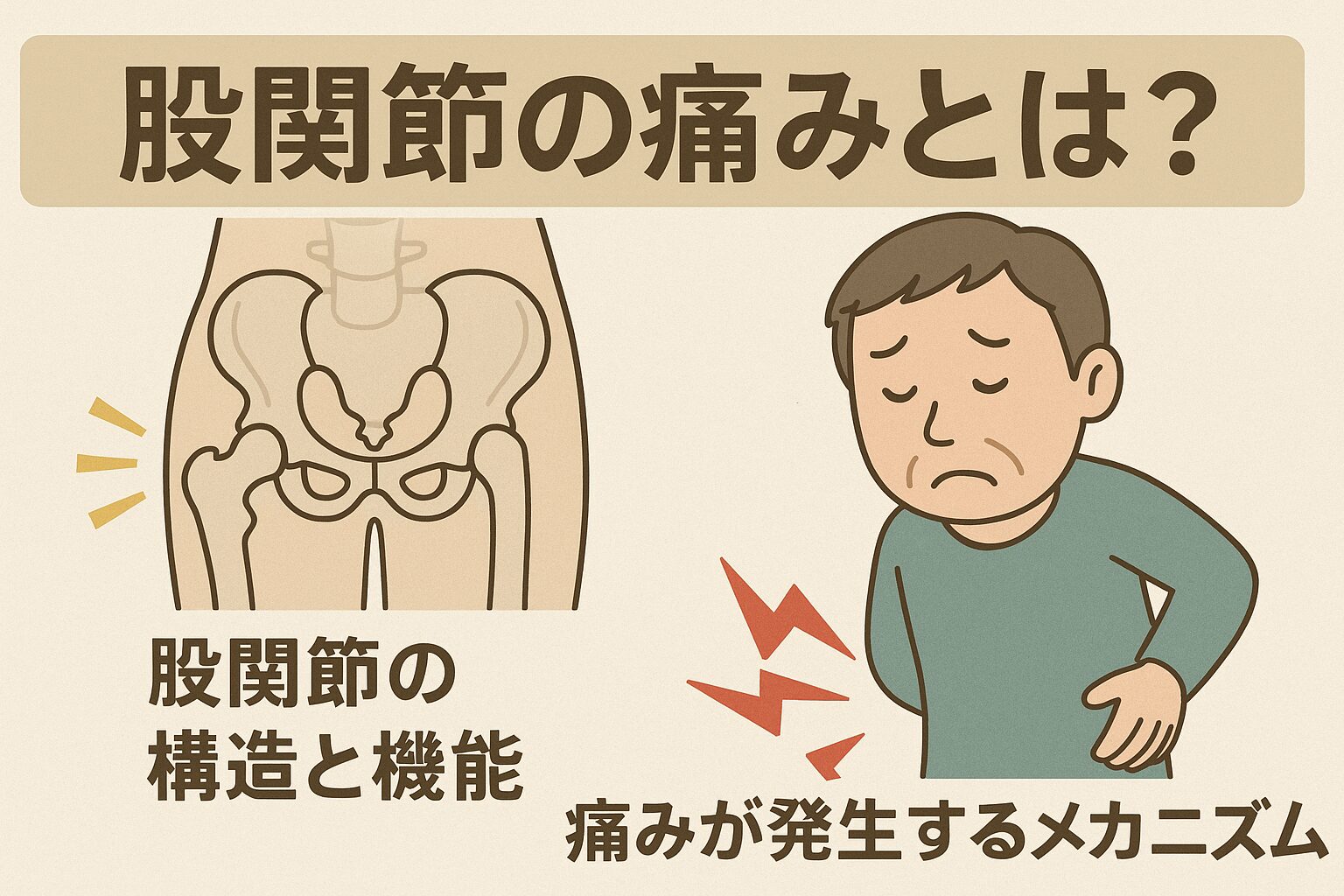
「最近、歩くたびに股関節のあたりがズキズキする…」そんな悩みを抱える人は少なくありません。股関節は、日常のあらゆる動きに関わる大切な関節であり、痛みが出ると生活の質に大きく影響します。まずは、股関節の仕組みと、なぜ痛みが起こるのかを見ていきましょう。
H3:股関節の構造と機能
股関節は、太ももの骨(大腿骨)の先端が骨盤のくぼみに収まる「球関節」と呼ばれる構造をしています。この構造により、前後・左右・回転など多方向の動きを可能にし、歩行や階段の上り下り、立ち上がりなどの動作をスムーズに行うことができます。
また、軟骨が関節部分を覆っているため、骨同士が直接ぶつからず、滑らかに動くことができます。さらに、関節包や靭帯、筋肉が周囲を支え、安定性と柔軟性を保っています。
H3:痛みが発生するメカニズム
股関節の痛みは、軟骨のすり減りや炎症、筋肉や靭帯の緊張などが原因で起こるとされています。例えば、変形性股関節症では、加齢や負荷のかかりすぎにより軟骨が薄くなり、骨同士がこすれ合って炎症を起こすと考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7329/)。
また、長時間の座り姿勢や運動不足によって、股関節周辺の筋肉が硬くなり、動かすたびに負担が集中することも原因の一つと言われています。こうした状態が続くと、違和感から痛みへと進行する可能性もあるため、早めの対処が大切です。

「股関節が痛むのって、年のせいかな?」と思っていませんか?実は、痛みの原因はひとつではなく、さまざまな要素が関係していると言われています。ここでは代表的な原因について紹介します。
H3:変形性股関節症
変形性股関節症は、股関節の軟骨が少しずつすり減ることで関節の動きが悪くなり、炎症や痛みが生じる状態とされています。特に女性に多いと言われており、歩くたびに違和感を覚える方も少なくありません。加齢に伴って起こることが多いですが、姿勢や運動習慣も影響すると考えられています(引用元:https://kumanomi-seikotu.com/blog/7329/)。
H3:関節リウマチ
関節リウマチは、自己免疫の働きによって関節に炎症が起こる疾患です。股関節に炎症が起きると、痛みだけでなく腫れや動かしにくさも感じる場合があります。早期に気づくことができれば、適切な検査や施術により負担を軽減できる可能性があります。
H3:筋肉や腱の炎症
股関節まわりには多くの筋肉や腱が存在しており、これらが使い過ぎや急な動作で炎症を起こすことがあります。ランニングや重い物を持ち上げる動作など、日常の何気ない動作でも負担が蓄積すると炎症につながることがあるとされています。
H3:姿勢の悪さや運動不足
長時間のデスクワークや猫背、片足に重心をかける立ち方など、悪い姿勢が習慣になると、股関節にかかる負担が偏ってしまいます。また、運動不足によって筋力が低下すると、関節をしっかり支えられず痛みの原因になるとも言われています。
H3:医療機関での検査方法
股関節の痛みが続く場合には、医療機関での検査が重要です。X線(レントゲン)やMRIによって、骨や軟骨の状態、炎症の有無などを確認できるとされています。画像検査によって、原因の特定と適切な施術につながると考えられています。

H2:股関節の痛みの症状と触診方法
「なんだか最近、歩くと股関節に違和感がある…」そんなふうに感じたことはありませんか?股関節の痛みは、ある日突然あらわれるというよりも、少しずつ進行していくケースが多いと言われています。ここでは、初期段階から進行時の症状までを整理しつつ、医療機関での検査についても紹介します。
H3:初期症状と進行時の症状
股関節の痛みが現れ始める初期段階では、「少し動かしたときに違和感がある」「立ち上がり時にズキッとする」といった軽い症状からスタートすることが多いようです。朝起きたときや長時間座ったあとの動き出しに痛みを感じるという人も少なくありません。
ところが、こうしたサインを放置してしまうと、次第に階段の上り下りや歩行すらつらく感じるほどの痛みに変わる場合があります。さらに進行すると、関節の可動域が狭まり、足を広げる・曲げるといった動作が難しくなるとも言われています
医療機関での触診方法
「ちょっと痛いだけだし、様子を見ようかな」と我慢してしまう方も多いのですが、股関節の痛みが続く場合は、医療機関での検査を受けることが大切です。検査方法としては、まず問診と触診を行い、その後X線(レントゲン)撮影で関節の状態を確認することが多いです。
X線では、軟骨のすり減り具合や骨の変形などが確認されるとされていますが、さらに詳しい情報を得るためにはMRI検査が活用されることもあります。MRIでは軟部組織(筋肉や腱、靭帯など)や炎症の有無も確認しやすいため、より総合的に状態を把握できると言われています。
H2:股関節の痛みの予防と改善策
「痛くなってからじゃ遅いよね」と思いながら、ついつい後回しにしていませんか?股関節の痛みは、ちょっとした日常の工夫で予防したり、悪化を防いだりできることもあると言われています。ここでは、すぐに取り入れやすい対策をいくつかご紹介します。
H3:日常生活での姿勢改善
まず意識したいのが、普段の姿勢です。座っているときに片足を組むクセがある方や、スマホを見るときに前かがみになる方は要注意です。こうしたクセは、知らず知らずのうちに股関節へ偏った負担をかけている可能性があるとされています。背筋を伸ばして座る、体の中心に重心を置くなど、少しの意識で変化が期待できるとも言われています
H3:適度な運動とストレッチ
「体を動かすのは苦手…」という方でも、簡単なストレッチやウォーキングなら取り入れやすいはずです。特に、股関節まわりの筋肉をほぐすようなストレッチは、痛みの予防に有効とされています。無理のない範囲で、継続することが大切です。
H3:体重管理の重要性
体重が増えると、当然のことながら股関節にかかる負担も大きくなります。その負担が蓄積すると、関節の軟骨がすり減る要因になることもあると考えられています。バランスの良い食事と適度な運動を意識して、体重を安定させることが股関節のケアにつながるかもしれません。
H3:サポーターや補助具の活用
「どうしても痛みが気になる」というときは、無理せずサポーターや補助具を取り入れることも一つの方法です。股関節を安定させたり、動きやすくしたりすることで、日常生活の中でも安心して過ごせる場合があります。ただし、使用方法やサイズ選びには注意が必要ですので、専門家のアドバイスを受けるのが安心です。
「痛みが長引いていて、どうしたらいいかわからない…」と困ってしまうこともありますよね。股関節の痛みがなかなか落ち着かないとき、できるだけ早めに適切な対処をすることが重要と言われています。ここでは、医療機関における検査の選択肢や専門家に相談する意義についてお伝えします。
H3:医療機関での検査方法
「病院に行ってもいいのかな」と迷ってしまうかもしれませんが、長引く股関節の痛みには、薬物療法やリハビリ、手術といった多様な方法が検討されると言われています。
例えば、炎症を抑える薬を使って痛みを和らげたり、リハビリで関節の機能を向上させるなど、その状態に合わせた検査が考えられるのです。
手術というとハードルが高く感じるかもしれませんが、関節の変形が進行している場合や日常生活に支障が出ているケースでは、手術が選択肢のひとつとして提案されることもあります。いずれにしても、自己判断は避けて、医師の意見を聞くことが大切です。
H3:専門家への相談の重要性
股関節の痛みは無理せず我慢するものではなく、まずは一度、医師や理学療法士,
整骨院や整体といった専門家へ相談することが勧められています。また、一見大した症状に見えなくても、適切な検査を受けることで大きな病気を早期に発見できると考えられています。
特に、専門家の意見をしっかり聞くことで、痛みの原因や適切な対処を知ることができ、安心して日常を過ごす一歩になるかもしれません。
ここまでご覧頂きましてありがとうございます。
今回は股関節の痛みについて色々ご解説させて頂きました。
もしあなたが現在股関節の痛みでお困りでしたら当院は股関節に特化した施術も行なっています。
もし、股関節の事でお悩みでしたら当院ご相談下さい。